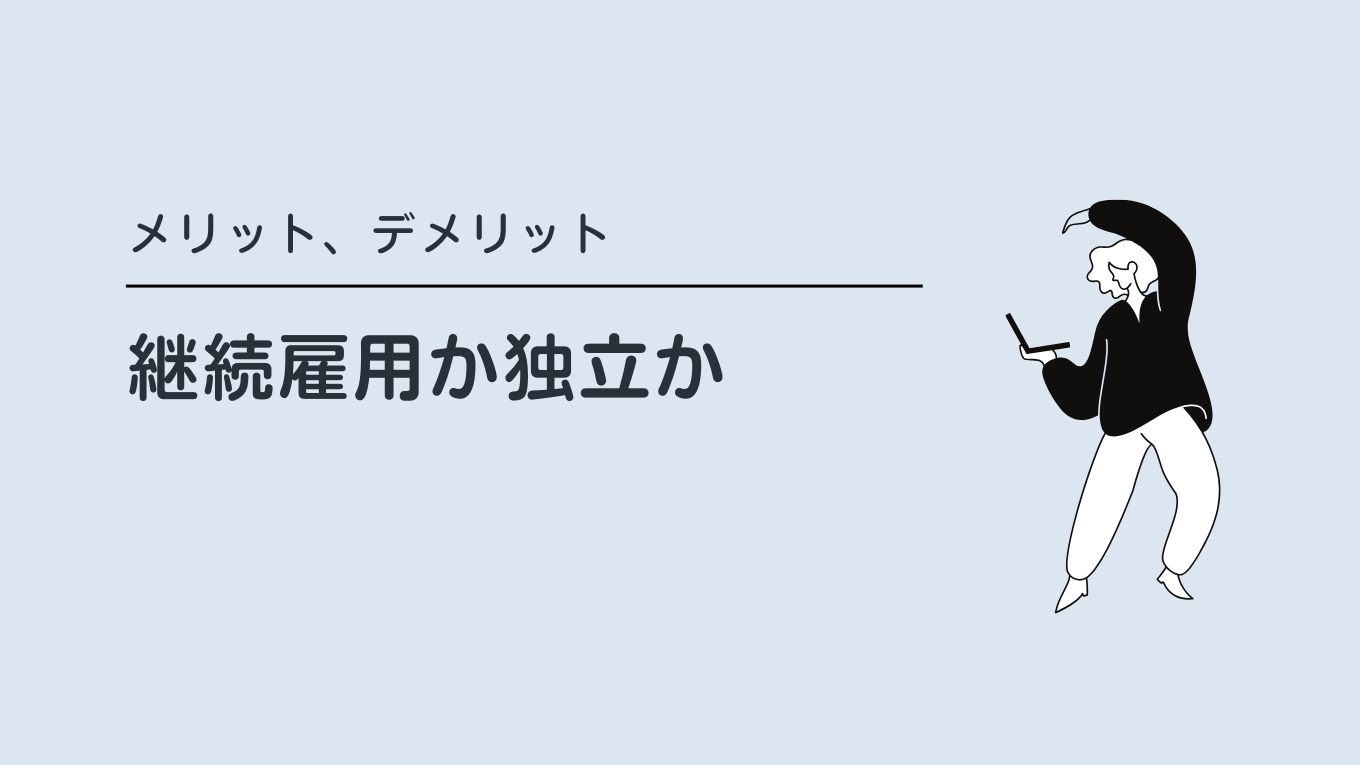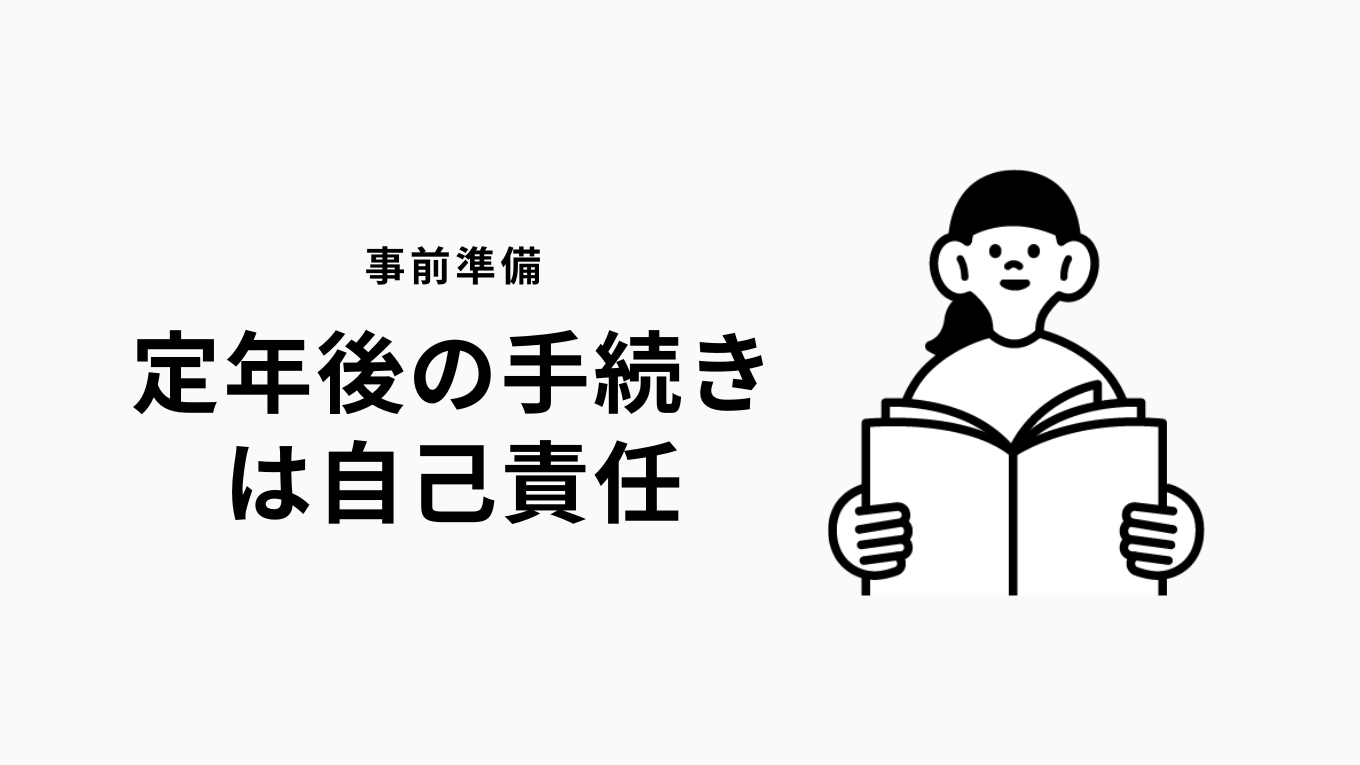定年前に会社を離れる人が準備すべきこと
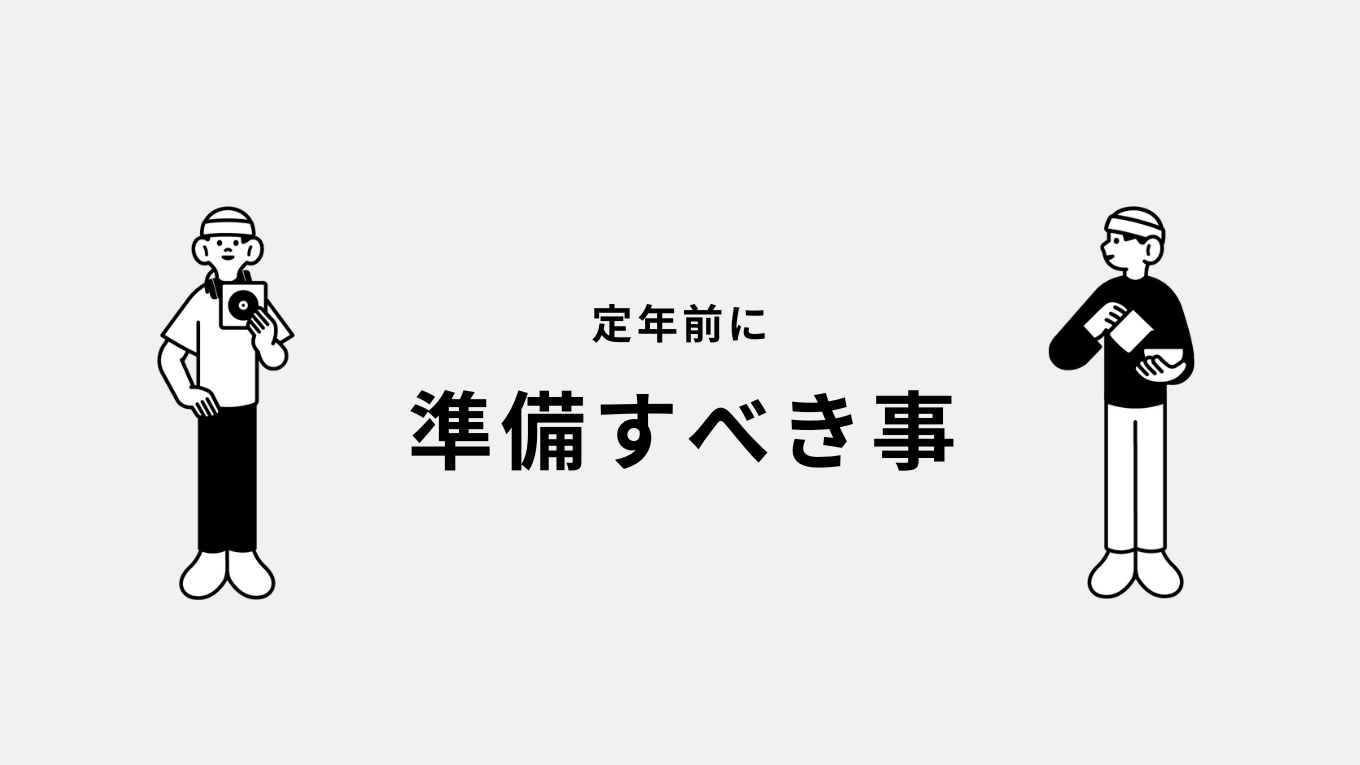
定年退職が近づいて来るとおおむね数年前に社内セミナーが開かれておおよその退職金の額や退職を踏まえて準備することの説明会がある。それを過ぎて、いよいよ退職日が数か月に迫ると総務に呼ばれて、具体的な退職手続きの説明を受けることになる。まあ、最低限の手続きであれば、以上のような会社任せでも大丈夫だ。ただ、定年後の生活を見据えて、「入りを増やし出を減らす」戦略を考えるのであれば、全くの準備不足となる。
では、どのような段取りを踏めば、「入りを増やし出を減らす」段取りを踏めるのか、ここでザッと説明しよう。
まず、気にすべき点は以下のとおりだ。
・健康保険
・国民年金
・所得税
・地方税
・消費税
・事業用の銀行口座
・事業用のクレジットカード
・確定申告の準備
・節税の工夫
・小規模企業共済
・セーフティ共済
・iDeCo
・自治体の福利制度
それに対してやるべき項目は以下のとおり。
・健康保険の任意継続手続き
・独立する場合は退職前から独立に掛かった領収書を取っておく。
・大学時代の未納の国民年金保険を払う
・年金事務所に行き、未納分があれば国民年金保険に加入
・国民年金保険に入った場合は、iDeCoに加入
・小規模企業共済に加入
・個人事業の開業届け
・Free等の会計ソフトの導入
・離職票の取得→ハローワークで求職
・失業保険を貰う
・自社HPの立ち上げ
・退職前にビジネス用のクレジットカードを作る。
・ビジネス用の銀行口座を作る
項目別の留意点
国民年金
・未納分があれば遡って支払い可能。
・将来の年金受給額が増え、支払った分は控除対象となる。
・iDeCo加入資格も発生する。
健康保険
・任意継続の手続きを行う。
・セーフティ共済にも加入を検討。
所得税・地方税
・小規模企業共済に加入。
・未納分の国民年金を支払うことでiDeCo加入も可能に。
・セーフティ共済で節税対策。
消費税
・免税業者と課税事業者、どちらで事業を始めるか判断して手続きを行う。
自治体の福利制度
・自治体が実施する中小企業勤労者・事業主向け福利厚生制度を活用。
失業保険
・個人事業主や業務委託に移行する前に、離職票を取得し失業保険を受給。
・職業訓練校に通う選択肢もある。
独立関連
・個人事業主として税務署に開業届を提出。
・事業用銀行口座を開設(ネット銀行や信用金庫でも可)。
・退職前にビジネス用クレジットカードを取得。
・自社HPの立ち上げ。
確定申告
・開業準備期間の経費も対象になるため、領収書を保存。
・会計ソフトを導入して早めに会計体制を整える。
定年退職は「終わり」ではなく、新しい生活や事業のスタートラインでもある。会社に任せるだけでなく、自ら主体的に準備を進めておくことで、安心感と自由度の高いセカンドライフを実現できるだろう。